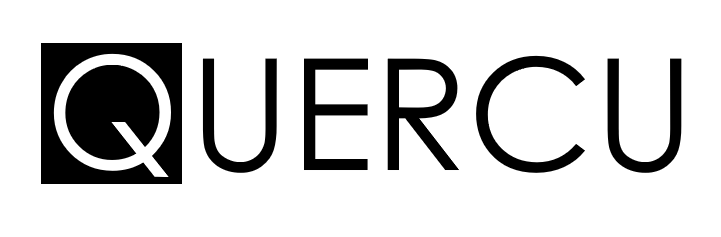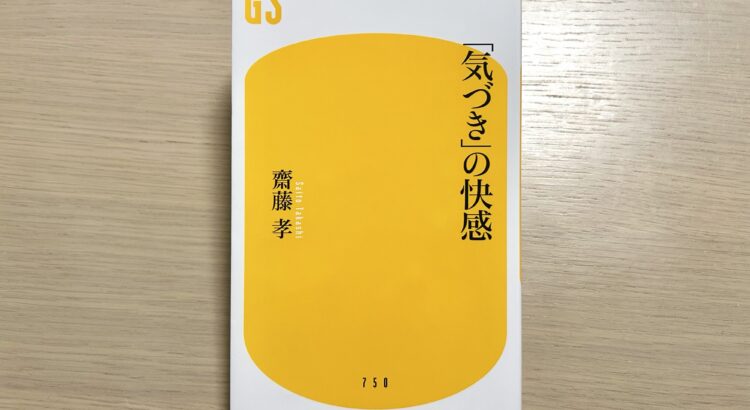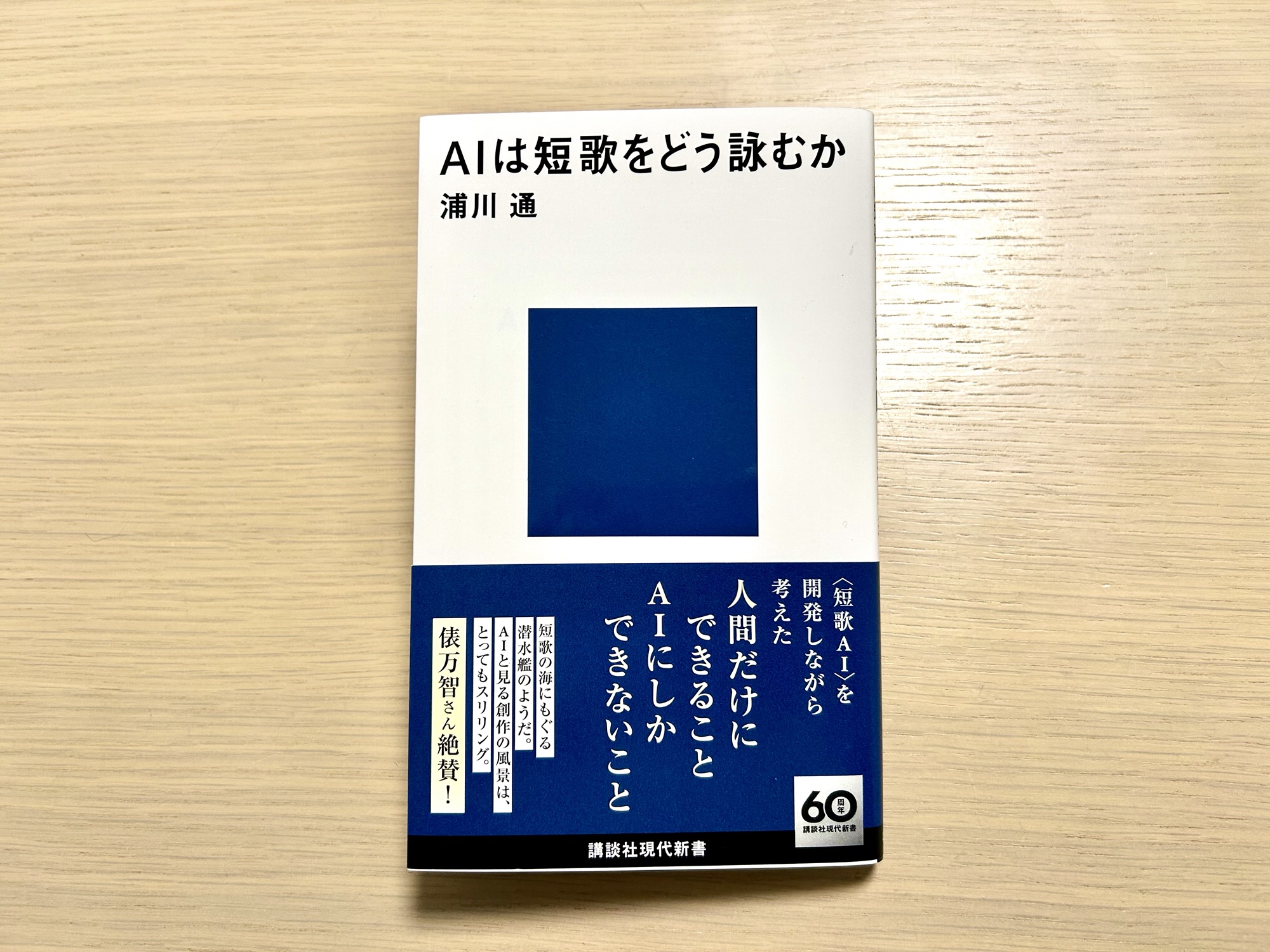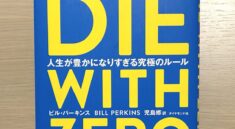目次
「気づき」とは何か
気づきとは、自分が今まで知らなかった事柄を新たに理解すること。知的好奇心を満たしてくれるもの。
気づきが多ければ多いほど、仕事での成果も上がり、人生が豊かに楽しくなる。
気づきを得るにはどうすればいいか
物事を客観視する・俯瞰で捉える
作中で非常にわかりやすい例えが挙げられていました。テレビでサッカーの試合を観ていて、一選手のパフォーマンスが落ちているから交代させるべき場面なのに、監督は交代させる気配がなくてもどかしい、というようなとき。
テレビの前の人はフィールドを俯瞰して見ているから一部の変化に気づきやすいが、俯瞰できないベンチ側からでは気付けるものも気づきにくい。だから物事は俯瞰して見る方がよい、ということでした。
※もちろんサッカーの試合では、監督は何かしらチームや試合状況を踏まえた上で交代させずにいるかもしれないから例として適切かと言われれば難しい、ということは作中でも書かれていました。
自分ごととして考える
傍観者から当事者へと意識をずれせば、気づきが起こりやすくなる。
「自分がこれをするとしたら、何をどう改善するか」など、自分ごととして考えることが重要である。
リフレッシュする・アイデアを寝かせる
リフレッシュするとはそのままの意味で、脳を休め思考をリセットするということです。
例えば、夜遅くに書いた手紙やメール。そのまま送らず、翌朝読み返すと「ここは書き直した方がいいな」と気づくなど。
アイデアを寝かせるというのも読んで字の如く、思いついたことはしばらく時間を置いて後で再検討した方が結果的に良いものができるということです。
このアイデアは寝かせるべきというのは、外山滋比古『思考の整理学』でも主張されていました。『思考の整理学』も面白い本なのでおすすめ。
基礎知識が大事
幅広く基礎的な知識を得ることは、気づきに繋がる重要な行動です。
例えば義務教育で少し習った歴史の出来事が、大人になってから観た映画の1シーンでパロディとして使われていることに気づくなど。「ああ、これはアレのことか!」という快い感動が得られるなど身近なことにも繋がります。
自分が気づいたことを発信・共有する
気づきを発信・共有することも、更に新たな気づきが得られる行動です。
例えばSNSで気づいたことを発信して、それに対して更に意見や気づきが他人から寄せられて、自分も新たな気づきを得られるからです。
まとめ
気づきに必要なことが多く挙げられていますが、どれも非常に簡単で誰でも実践ができるものです。
ここでは目次を一目見るだけ、気づきを得るには何をすべきか分かるよう、端折りに端折ってまとめて書いています。各項目の詳細やエピソードを詳しく読みたい方は、本を手にとって開いてみてください。