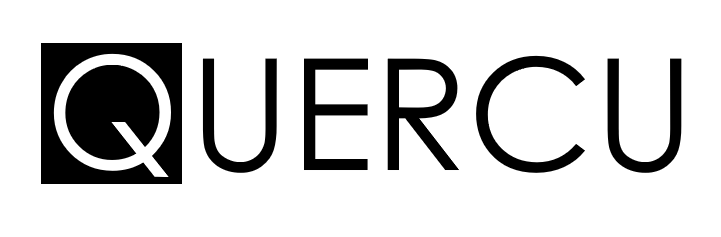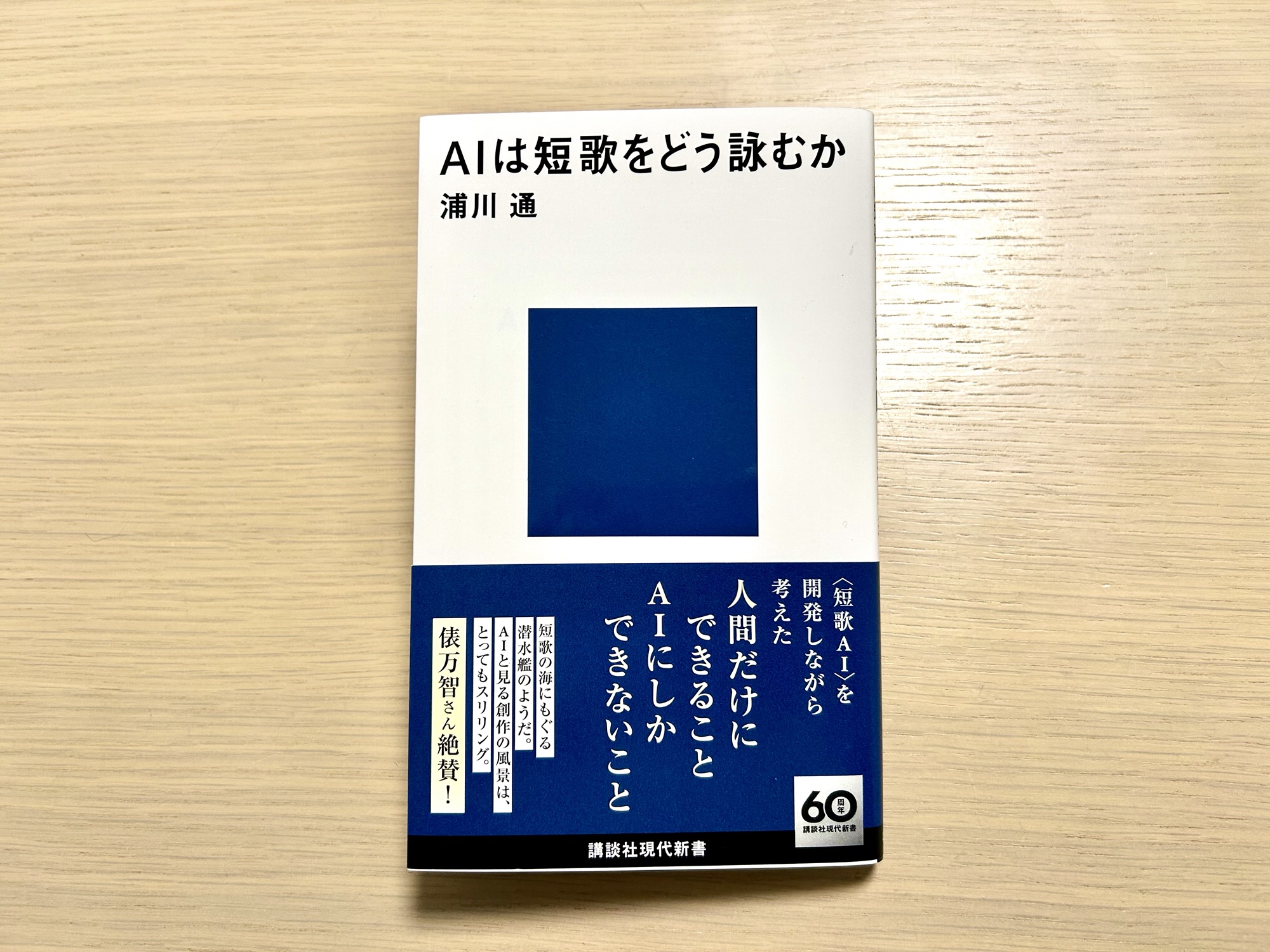ジュンク堂の新書コーナーをそぞろに歩いていると、浦川通『AIは短歌をどう詠むか』(講談社現代新書)の表紙が目に留まって、1秒も考えることなく買い物カゴに入れました。
曲がりなりにも同人で一次創作をする人間として、AIとどう付き合っていくかをずっと考えていたためです。
はじめに少し本の内容を紹介して、その後一次創作同人マンとして考えたことを徒然と書き連ねようと思います。
目次
『AIは短歌をどう詠むか』はどんな本か
著者の浦川さんは、朝日新聞社メディア研究開発センターでコンピュータが日常の言葉を処理する「自然言語処理」技術の研究開発を行っている方です。
端的に言えば、AIに自然な会話文や文章を学習させ、それを翻訳したり、ある部分を要約させたりする技術の開発です。
その研究開発にあたって、また歴史ある歌壇を持つ朝日新聞社※という環境もあって、AIに短歌を生成させることになったそうですが、細かいことは本書の序章と第1章にあります。詳しく知りたい方は一読ください。
※朝日新聞の「朝日歌壇」は、1910年に石川啄木が選者となって始まった。
また、第4章までは生成の仕組みの解説や、実際の生成された短歌や、歌人・俵万智さんとのやりとりなどが書かれています。
創作者として気になる第5章
「AIと人間」という文脈になるとどうしても「勝ち負け」で語られがちだが、果たしてそれで議論を済ませても良いのか、というのが著者の問いかけです。
確かに、チェスや囲碁でAIは人間のチャンピオンに勝利していますが、短歌のように成果が勝ち負けでは計れない分野でAIはどう在れば良いのかというのはごく自然な問いだと思います。
しかしながら著者は「短歌の作歌にもテクノロジーが積極的に応用されるべき、という立場ではない」と明言しています。そしてAIには壁打ち相手としての役割を担わせることを提言しています。
ここでいう壁打ちとは、自分が完成させられない短歌の上の句を与え、下の句を複数生成させてその中から良いものを、ああでもないこうでもないと考えて自分が言い表したかったものを選ぶということを言います。
またAIを壁打ち相手として使うとともに、鏡のようにも使うべきとも論じています。少し長いですが引用します。
”「鏡」は、私たちが社会的な生活を送る上で欠かせない道具です。
(中略)他人と相対してやり取りする前に、いまの自分がどのような姿なのかを確認する作業が、そこでは行われます。そして鏡は正直です。
例えば「寝癖があることを伝えたら、気分を悪くするかもしれない」といった気遣いや忖度といったものは当然なく、いつでもありのままのあなたをうつし出してくれるところに、ほかには代え難い価値があると言えるでしょう。
一方で、自分の普段の言葉づかいがいったいどのように見えるのか、それを客観的に把握するのは、そう簡単な作業とは言えません。
(中略)先ほど、人間である自分が考えている上の句から、言語モデルに下の句を付けさせる、といったことを試してみましたが、これは私の意図や人柄を知らない知性が続きを書いている、とも捉えることができます。
これを応用することで、私が書いた歌を客観的に眺める鏡のような道具にする、そんな可能性もあるように思います。”
創作は客観性を意識していても、やはり生み出した苦労や、気に入った表現方法など思い入れが邪魔をして客観視することは難しい。そこでAIを”鏡”として利用しようという主張です。
言葉を使う創作において、このAIの使い方はとても理にかなっているように思います。
しかしながら、ここ最近巷間で議論になっている、絵におけるAIの使い方にこれを当てはめるのは非常に難しいのではないでしょうか。
AIで絵を描くことの是非
自分としては「用途によって是非が異なる」としか結論が出せません。
例えばブログ記事のアイキャッチに、文章からのイメージとしてAIによって生成された絵を使うことは許容されても良いと思っています(現に最近のウェブニュースなどの記事ではその傾向が顕著に増えています。)
なぜ許容できるかといえば、ブログ記事そのものは独自性を持つ著作物であっても、その文章から抽出した言葉を元に生成したイメージ画像そのものには独自性がないからです。
一方、生成した絵そのものを「描いた絵」として扱うこと、生成した絵を独自性のある創作物と呼ぶのはやはり無理があると言わざるを得ません。
プロンプトと呼ばれる生成に必要な命令文は、仮に考えに考えて書いたとしてもそれはあくまでプログラムへの指令に過ぎません。
生成された絵は、その指令を基にインターネット上から指令に見合った絵を寄せ集め、混ぜこぜにして構築しなおしたものです。この生成の過程を考えると、そこに独自性はなく、創作物とは非常に言い難いのではないでしょうか。
AIにプロンプトを与えて成果物の生成を待つAIイラストと、AIに下の句を生成させて自分の表現したかったものを探して添削をする作業が全く同じであると私には言えません。
ただこれも、例えば「可愛いポーズ」を複数生成させて、その中から気に入ったものを選びそれを基にしてイラストを描くといった、ポーズ写真集やデッサン人形のような使い方であれば、許容されて然るべきと思います。
まとめ
創作における作業工数を減らし、創造のための時間を生み出すようなAIの使い方には大いに賛成です。
ここでいう創造のための時間とは、絵画、文芸、音楽、映画、漫画などに触れ、様々な人と交流し、あちこちに出かけるなどのインプットする時間のことです。
インプットがないと、創作のための源泉が枯れてしまい、アウトプットができなくなります。
AIが、創作する人の良き隣人となる日が1日も早く来てほしい。そう願って止みません。